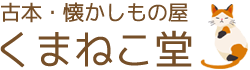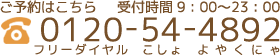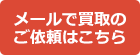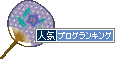高橋泥舟(幕末の三舟)の筆筒(2)
カテゴリー/出張買い取り/骨董品・古いもの/くまねこ堂通信
昨日の記事の続きです。
勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟(でいしゅう)の3人は、
幕末明治に活躍した幕臣で、
「この三人が協力して、戊辰戦争の際に江戸を戦火から救い、
内戦を回避して、外国(英仏)の介入をふせぎ、日本の独立を守った」
という功績を評価され、「幕末の三舟」と並び称されるようになったそうです。
しかし、勝海舟や山岡鉄舟に比べますと、
今回ゆかりの品が入りました高橋泥舟の知名度は、
残念ながら低いと思われます。
その理由の一つとして、泥舟が明治に入ると
「自分は徳川幕府につかえていたのだから、明治天皇には仕えない」
ときっぱり職を辞し、隠遁生活を送ったことが挙げられます。
それについて、竹内好はこう述べているそうです。
———————————————————————————–
高橋泥舟という人は槍の名人で慶喜の守護をやったわけだが、
そんなことはどうでもいいとして、その後に一度も明治政府に士官しないのです。
慶喜の護衛の役が終わったら、すっかり引退してしまった。
そして字がうまいし、絵もうまいので、書画で生活した。
いつ死んだかもわからないような消え方をした。
それが私は好きなんですよ。一種の非転向なんですがね。
過剰な任務を自分に課さないという、そういう生き方が、私は好きなんです。
———————————————————————————–
泥舟は明治以降は、書家の鑑定などをして生計を立て、隠遁生活を送りました。
晩年は髑髏の絵を好んで描いていたそうで、
「人間は最後はみんな髑髏になってしまうと考えれば、
生きているときの栄華とか美貌などにとらわれるのは嫌だ。
そんなものにとらわれる人間というのは愚かなものだ。」
という内容の随筆を残しているそうです。
しかしこういった、教科書や本の中でしか知らない歴史上の人たちが
実際に使った品々が入ってくるなんて、なんて面白いお仕事なのだろうと思います。
品物を手に取ると、活字の中でしか知りえないその人が確かに存在し、
生きていたのだという息吹が感じられるような気がいたします。
参考文献:
「幕末の三舟 海舟・鉄舟・泥舟の生きかた」松本健一著/講談社選書メチエ
よろしければシェアお願いします
2014年8月に投稿した古本出張買取り│くまねこ堂・妻のブログの記事一覧